「奨学金の返済があるから、お金は貯められない」
そう考えている人は多いのではないでしょうか。
私自身も、大学卒業時には奨学金400万円という重い借金を背負っていました。しかし今、30歳手前にして資産1500万円を築けています。
今回はそのリアルな家計簿を公開しつつ、どうやって返済と資産形成を両立させたのかをお伝えします。誰にでも実践できる節約術も盛り込んでいるので、ぜひ参考にしてください。
奨学金があっても資産形成は可能なのか?
奨学金400万円という額を見て「自分には無理」と感じるかもしれません。ですが、実際の返済額は月16,000円程度。大きな負担に見えても、正しく家計を管理すれば資産形成は十分可能です。
そのカギとなるのが、家計を“黄金比”で整える 「5:3:2の原則」 でした。
家計の黄金比率「5:3:2の原則」とは?
可処分所得を以下の割合で分けるシンプルな家計管理法です。
- 50%:生活費(家賃・食費・光熱費など必須支出)
- 30%:娯楽費(趣味・教育・交際費など生活の質を高める支出)
- 20%:貯蓄・投資(将来の資産形成)
このルールを守ると、我慢せずに自然と資産が増える仕組みを作れます。
実際に私の家計簿も、この比率にかなり近い形になっています。
先月の家計簿を大公開
資産形成の話は抽象的になりがちですが、やはり気になるのは「実際にどういう支出をしているのか?」という具体的な数字でしょう。
私の手取りはおおよそ24万円。そのうち奨学金返済1.6万円をまず差し引き、可処分所得224,000円をベースに家計を組み立てています。
生活費などの諸経費は妻と完全折半し、そのうえで各自の娯楽費などを追加しています。
以下は折半後の私個人の支出です。
家計簿の詳細
| 項目 | 金額 | 割合 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 生活費の部 | 125,183 | 56% | |
| 住宅(家賃) | 60,000 | 快適さを重視し3LDKの築浅物件 | |
| 食費 | 28,092 | 基本は自炊中心 | |
| 日用品 | 12,523 | 消耗品・日常雑貨・子ども用品 | |
| 水道・光熱費 | 13,080 | 季節による増減あり | |
| 通信費 | 7,743 | 固定回線+格安SIM | |
| 交通費 | 1,080 | 通勤費は会社負担 | |
| 健康・医療 | 2,665 | 定期検診・市販薬 | |
| 娯楽の部 | 71,390 | 32% | |
| 教養・教育 | 17,939 | 子どもの保育園+新聞 | |
| 趣味・娯楽 | 4,189 | アウトドアなど | |
| 交際費 | 3,000 | 友人との食事やプレゼントなど | |
| 衣服・美容 | 3,200 | 毎月の美容院代、服は基本買わない | |
| 投信(NISA) | 10,000 | 全世界株式 | |
| 投信(iDeCo) | 20,000 | 全世界株式 | |
| 投信(特定口座) | 14,262 | 債券・金など分散投資 | |
| 仮想通貨 | 2,000 | ETH現物 | |
| 貯蓄の部(預金) | 27,427 | 12% | 生活費と娯楽費の余剰分 |
結果として、生活費56%・娯楽32%・貯蓄12%。
「5:3:2の原則」に近いバランスになっています。
投資を“娯楽”にする
おっしゃりたいことは分かります。
無理なく節約する方法を共有するのがこのブログの方針ですが、実は私にとって投資は娯楽そのものです。
資産が増えていくのを眺めるのが、私にとって一番のストレス発散です(笑)。
20代のうちに資産1000万円を築くためには、投資を趣味にし、楽しむことが最大の近道だと思います。
まずは毎月1万円からでも良いので積立を始めてみましょう。
楽しさが分かれば、そのうち積立額を増やしたくなり、資産額も頭一つ抜けるようになります。
生活の質を下げない節約術 ― 固定費カットが最強
とはいえ、誰でも簡単にすぐできる方法を共有するのが当ブログのポリシーですので、
今すぐでき、更に生活の質を下げずに楽に節約できる方法があります。
それは固定費の削減です。
スマホ代の見直し
生活の質を下げずに真っ先に固定費を削減する方法はスマホのキャリアを格安SIMに変えることです。
私は日本通信SIMを利用しています。
- 月額:1,390円(税込)
- データ容量:20GB
- 通話:70分まで無料(純正通話アプリ対応)
大手キャリアとの差額は月3,000円程度。つまり年間約36,000円の節約。
もし楽天経済圏ユーザーでスマホのみ利用なら、楽天モバイルもおすすめです。固定回線をやめてスマホに1本化すれば、月3,278円に通信費を抑えることができます。
電気代について
2020年ごろは新電力が有利でしたが、現在は割高傾向。
安定性と価格を考えると、大手電力のままが無難です。
尚、我が家はオール電化でして、深夜料金が安くなるプランで契約しているのですが、
無理せず電気代を浮かせる為に以下のささやかな工夫を行っております。
- ご飯は毎日都度炊くのではなく、週に1~2回に5合をいっぺんに炊く。
⇒炊飯にかかる電気代は1合でも5合でも同じなので、一気に炊く方がお得です。
すぐに冷凍をすれば品質に問題なく1週間は余裕で保存できます。 - IoTプロダクトの活用
⇒そんなに熱くない日や家を空けるとき、ついエアコンを付けっぱなしにしてしまいますよね。
忘れずに消す!という精神論では節約は長続きしないので、仕組化が重要です。
それをするにあたり、私は”Nature Remo”という製品を愛用しております。
これを使うと室温や時間帯を閾値にして自動でエアコンのON/OFFをしてくれるので、
塵積で電気代の節約を行うことができます。
私は忘れっぽい性格で、本当に週に1回くらいはエアコンを消し忘れてましたが、
Nature Remoを使いだしてからそれは全くなくなりました。
かれこれ5年くらいは使い続けており、出勤時に自室のエアコン、就寝時にリビングのエアコンを消し忘れを防げたことにより節約できた金額を以下に試算してみました。
| 週に1回ずつ消し忘れ | 年間消費電力量 | 年間電気代 | 6年間繰り返した場合 |
|---|---|---|---|
| 出勤時(9時間) | 374.4(kWh) | 約10,108円 | 約50,540円 |
| 就寝時(9時間) | 332.8(kWh) | 約8,986円 | 約44,930円 |
| 合計 | 707.2(kWh) | 約19,094円 | 約95,470円 |
こうして可視化してみるとものすごい得してることに自分でも驚きました。
そして、Nature Remoの価格はなんと6480円です。
単純な装置の為壊れにくく10年使えるとして、自室とリビングに1つずつ置くとして、12,960円の投資をすることで約19万円の節約ができることになります。
更にこの製品を推せるポイントなのが、夏場などはエアコンをONにする時間を帰ってくる30分前程度で設定しておくと、帰宅してすぐに部屋で涼むことができます。
「エアコンのタイマー機能でいいじゃん」と思う方もいらっしゃると思いますが、アプリを通して出先で遠隔操作もできるため、急に帰る時間が変わった場合でもすぐにエアコンの操作ができます。
さっきからエアコンのことしか触れてませんが、テレビや部屋のシーリングライトなど、リモコン操作できるものは大体対応しておりますので、使い方はあなた次第です。
生命保険・医療保険への加入は基本的に不要
入院リスクの現実
厚生労働省「令和5年患者調査」によると、人口10万人あたりの年間入院受療率は945人。
つまり約0.945%(100人に1人程度)に過ぎません。
平均入院日数は以下の通り:
- 35~64歳:約27.3日
- 15~34歳:約14日
つまり、60歳までに何度も入院する確率はかなり低いのです。
保険料と給付の損益分岐点
仮に入院日額5,000円・入院上限60日の医療保険に年間3万円で加入するとします。
- 60日入院 → 30万円の給付
- 保険料 → 10年間で30万円
しかし60歳までに60日以上入院する確率は極めて低く、大多数の人にとって支払う保険料の総額 > 受け取る給付金となります。
保険より資産運用にベットする
このため私は、低確率のリスクより高確率で伸びる資産に資金を回す方が合理的と考えています。
- iDeCo・NISAに月3万円を投資
- 万一の入院費は預貯金や投資資金から拠出
※iDeCoは60歳まで引き出せないため、不安な方はNISA優先でも十分です。
不要なサブスクは解約、必要なら惜しまない
不要なサブスクは即解約
総務省の調査によれば、世帯の平均サブスク契約数は4.3件(2023年)。
そのうち「ほとんど利用していないサービス」がある世帯は約35%。
例:
- 動画配信を複数契約しているが、観るのは1つだけ
- 音楽サービスを契約しているが、月に数曲しか聴かない
- ジムを契約しているが週1回も行かない
こうした“幽霊サブスク”は即解約です。
必要なサブスクは投資と考える
一方で、生活の質を確実に高めるサブスクはお金を惜しむべきではありません。
以下に私が契約しているサブスクをご紹介します。
Spotify(月額980円)
- 毎日の通勤や休憩中に音楽を聴いて心をリフレッシュしています
- 音楽はストレスホルモン(コルチゾール)を減少させる研究結果もあり
→ 心の健康に対する投資
マネーフォワード ME(月額500円)
- 銀行・証券口座と連携して資産を見える化
- 支出を把握でき、資産形成のモチベーション維持に直結
→ 実際に、1500万円の資産を築く大きな助けになったと実感しています。
サブスク見直しの基準
- 月5回以上利用しているか
- 生活の質を高めているか
- 無料の代替手段がないか
- 資産形成の妨げになっていないか
この基準で選別すれば、本当に必要なサブスクだけが残ります。
奨学金を返済しながら資産を築く4つのコツ
- 返済は手取りから天引きする
給料日に返済用口座へ自動入金。 - 「5:3:2」の原則で管理
生活費5割・娯楽3割・貯蓄2割。 - 固定費削減=投資資金へ
スマホ・保険・サブスク削減分をNISA積立へ。 - 楽しみながら投資を継続
家計簿アプリで資産の増加を可視化しモチベUP。
まずは自分の家計簿を「5:3:2」に当てはめてみてください。
小さな改善が、将来の大きな安心に変わります。
次回は実際に私が利用している投資信託と、その運用成績を公開予定です。
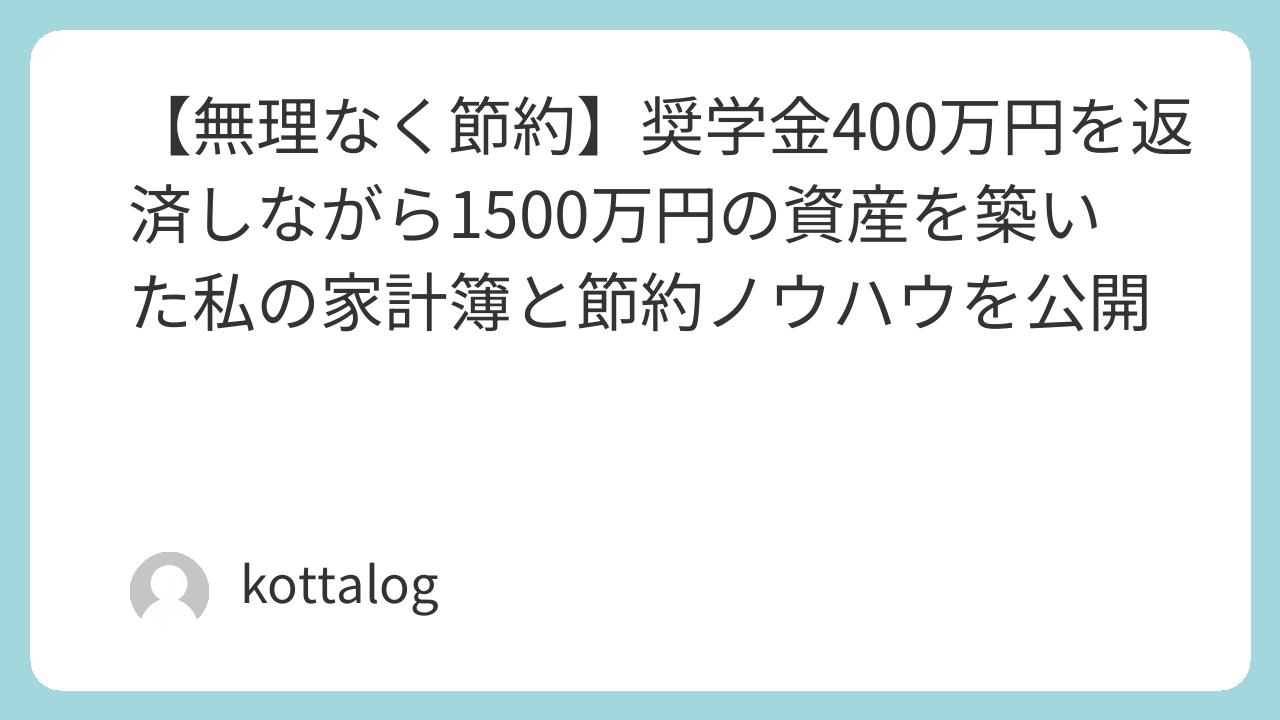
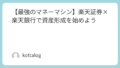
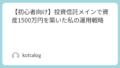
コメント