こんにちは、コタです。
今日は、奨学金を返しながらも積立投資をきちんと回すための現実的なキャッシュフロー設計を、私の実例ベースで公開します。ポイントは、借金の返済など絶対に必要な支払い後の所得で家計をルールを設計すること。そして、物価高など何があっても家計のルールを守るにすることです。
まず順番をルール化する
私は以下の順番で月次の順番は、次のとおりです。
- 給与を受け取る(手取り24万円)
- 絶対支払いが必要な金額を控除(月々4万円程 内訳は奨学金の返済:1.6万円、 子どもの教育資金:2万円、その他小口ローン返済:5000円程)
- 残り約20万円を可処分所得とし、2割を貯蓄・投資に先取り
この順番にしてから、意識せずとも借金返済、子供の教育費積立、投資を無理なく両立できてます。理由はシンプルで、返済・将来の約束(学費)・小口ローンのように「必ず払うもの」を先に抜き、自由に配分できる可処分部分の中で家計を設計するから。
やり方を毎月変えると、感情や相場に左右されます。お金の流れを固定しておけば、物価が上がっても、相場が荒れても、家計の大枠は崩れません。
可処分所得に「6:2:2」の配分を適用
理想は生活費5:娯楽3:貯蓄・投資2ですが、最近は物価上昇に賃上げが追い付いていない為、可処分部分(上記2を差し引いた後)に対して、生活費6:娯楽2:貯蓄・投資2の配分をかけています。
※勿論手取りに余裕のある方は5:3:2にしてください。
数字で確認しましょう。
- 手取り:240,000円
- 先に払うもの合計:16,000 + 20,000 + 5,000 = 41,000円
- 可処分部分:240,000 − 41,000 = 199,000円(約20万円)
この約20万円に対して、
- 2割(=約40,000円)を貯蓄・投資に先取り
- 残り(約16万円)を生活費6(約12万円):娯楽2(約4万円)で配分
こうすると、借金返済や教育費といった「絶対必要な支払い」を守りつつ、生活の満足度(娯楽)も確保し、将来の備え(貯蓄・投資)にも一定額を回せます。どれか一つに偏らないのがメリットです。
「2割」の内訳(貯蓄+投資の先取り設計)
私の「約4万円」の中身は、以下の通りです(※自動積立設定で先取りしています)。
投資(計32,500円)
- iDeCo:20,000円/月(全世界株式)
老後資金の土台。節税メリットが大きいので最優先枠。価格変動は気にせず、機械的に拠出。 - 特定口座:10,000円/月(債券・ゴールド・REIT)
株式暴落時の為のバッファとして購入してます。 - 仮想通貨:2,500円/月(ETH)
仮想通貨は将来もっと伸びると考えてますので、資産の5%~10%を目指して積立てます。
貯蓄(7,500円)
- 生活防衛資金や突発出費へのバッファです。
1年で90,000円の予備費ができ、家電の故障など突発的な出費に対応できます。
投資信託と違ってすぐに出動できる現金があるとそういう時安心です。
※今年はエアコンが故障し買い換えたので既にバッファは使い果たしてしまいましたが;;
ポイント:
「投資だけでなく現金バッファも2割に含める」ことで、あらゆる事態に柔軟に対応できます。投資を継続するために、現金クッションは必要装備です。
ボーナス月はNISAに集中+年齢%でリバランス
NISA枠は年2回(ボーナス月)にまとめて入れます。普段の生活費や返済を圧迫しないため、そしてリバランスの最適タイミングにするためです。
- NISA原資:ボーナス+余剰預金(月々貯めてた預金)
- リバランス基準:安全資産=年齢%(例:30歳なら30%を債券や現金などへ)
- 実行方法:ボーナス入金時に、
- 株式が増えすぎていれば債券・ゴールドを買い増し
- 安全資産が多すぎれば株式を買い増し
- 売って整えるより買い足して整える方針でコスト・心理負担を軽く(ノーセルリバランス)
この設計が機能する理由(メリット3つ)
- 返済と資産形成を同時進行
完済後にゼロから投資を始めるより、複利の立ち上がりが早い。 - 物価高でもルールで折れない
可処分部分に6:2:2をかけるため、生活と楽しみと将来のバランスを自動でキープ。 - 分散設計でブレにくい
株式(iDeCoの全世界)+債券・金・REIT+現金バッファ+小口の暗号資産。どれかが不調でも全体が壊れにくい。
実務の運用ルール(小ワザ集)
- 全部自動に:
給与日翌営業日に、返済・学費・ローン・投資・貯蓄が勝手に仕分けされるよう、引落し&自動積立に設定。 - 資産の成長を見守る:
iDeCoやNISAなどはマネーフォワードMEなど家計簿アプリで気が向いた時に評価額をチェック。
伸びているのを可視化することで資産形成のモチベーションアップ。 - 月初の家計予算決め:
月初に家計簿の予算を決め、生活費:6、娯楽:2、投資/貯蓄:2になるよう予算を調整。
※今月友達と飲みに行く予定があるならゲームの予算を削るなど。 - 繰上返済の判断軸:
奨学金やローン金利が高い場合は、投資より繰上返済のほうが確実にリターンになることも。金利と税引後期待リターンで比較。 - 将来のスライドアップ:
iPhoneローンが終わったら、その5,000円を丸ごと投資枠へスライド。可処分額を増やさずに、投資だけが育ちます。
よくあるつまずきと対策
- つまずき①:生活費が足りなくなる
→ 可処分部分の6:2:2の2(娯楽)を一時的に削って調整。貯蓄・投資の2は死守。
生活費⇒貯蓄⇒娯楽の順にお金を分配していく。 - つまずき②:NISAの一括が怖い
→ ボーナス一括+月次つみたての併用も可。心理的に楽なほうを選ぶ。 - つまずき③:株式など特定のアセットの割合が膨らむ
→ リバランス日に事前に決めたアセットアロケーションになるよう調整する。
各アセットの現状の金額と目標の金額の差額を計算し、目標額になるよう売買する。
まとめ:順番と比率で迷いの余地を消す
- 順番:給与 → 借金返済/教育費 → 残りの2割を貯蓄・投資
- 可処分部分の配分:生活費6:娯楽2:貯蓄・投資2(物価高騰の為この比率、理想は5:3:2)
- 2割の中身:iDeCo 2万円(全世界株式)、特定口座1万円(債券・金・REIT)、ETH 2,500円、現金7,500円
- ボーナス月:NISAに充て、年齢%で安全資産へリバランス(30歳なら債権&現金30%)
相場も物価も自分ではコントロールできません。だからこそ、自分で決めた順番と比率に家計の運営を委ねる。
これが、返済・教育・現在の生活・将来資産を同時に回すための最短ルートだと実感しています。
この記事を読んで積立NISAを始めてみたいと思った方は、以下の記事も書いてますので是非見てみてください。
【最強のマネーマシン】楽天証券×楽天銀行で資産形成を始めよう
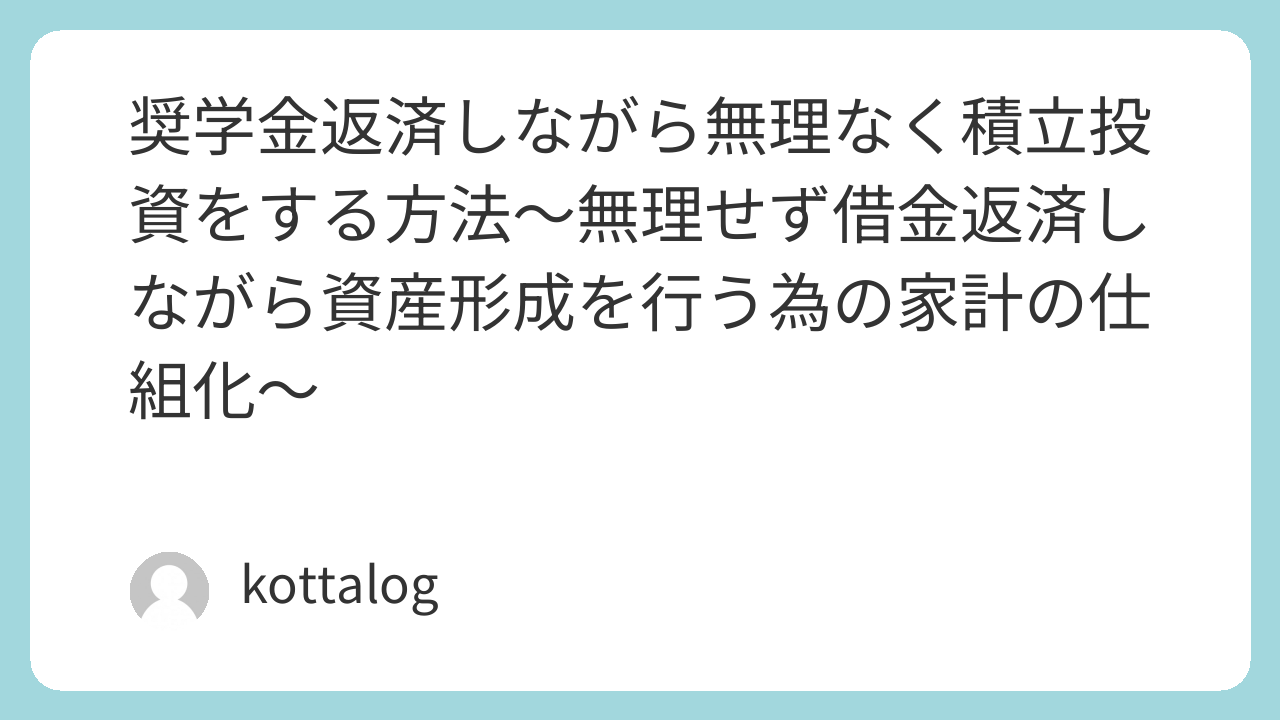
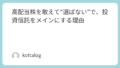
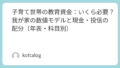
コメント