子育て世帯にとって「教育資金」は、家計を大きく左右するテーマです。
「大学まで公立ならそこまでかからないでしょ」と思う一方で、実際に必要な金額や備え方が見えにくいのが現実です。
今回は、高校まで公立・大学は家を出て県外の私立という前提で、我が家の教育資金シミュレーションを紹介します。現金と投資のバランス、そして“学資保険は使わない”という判断も含めて、リアルな計画をまとめました。
わが家の前提条件
- 幼稚園〜高校:すべて公立
- 大学:自宅から通える私立文系
- 習い事:ピアノなど月1万円程度
- 中学から塾に通う想定
- 保育料:3歳から無償化
- 積立方法:3歳〜15歳まで、夫婦で月4万円を全世界株式(オールカントリー)に投資
- NISAは利用せず、課税口座(特定口座)で積立
- 学資保険には加入しない
教育費 年表と概算シミュレーション
| 年齢 | 学年 | 年間支出(概算) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳 | 保育園 | 約6万円 | 入園準備・衣類など |
| 3〜5歳 | 幼稚園 | 約5万円 | 行事費・給食費 |
| 6〜11歳 | 小学校 | 年8万円 | 学童・修学旅行など |
| 12〜14歳 | 中学校 | 年15万円 | 塾・部活費・制服 |
| 15〜17歳 | 高校(公立) | 年30万円 | 進学塾・模試・受験費用 |
| 18〜21歳 | 私立大学(自宅) | 年200万円 | 学費・生活費 |
合計:約580万円(22年間)
これはあくまで標準的な試算。私立中高や留学を選べば、ここに数百万円上乗せされます。
現金と投資の配分モデル
現金:300万円を確保
現金は、以下に備えて確保します。
- 中学〜高校の塾代(短期で必要になる)
- 受験費用・模試代(まとまって支出)
- 医療費や突発支出(予備費)
「現金300万円」を目安に確保しておけば、急な支払いにも慌てず対応できます。
投資:月4万円×13年=624万円+運用益
3歳から15歳までの13年間、夫婦で月4万円を投資信託(オールカントリー)に積立。
- 元本:624万円
- 想定利回り:年5%
- 15歳時点の評価額:約850万円
この投資分を大学費用の原資に充てる計画です。
学資保険に入らない理由
教育資金といえば「学資保険」をすすめられることもあります。
しかし我が家では加入しません。
理由はシンプルで、コスパが悪いからです。
- 返戻率は高くても105%程度(10年で+5%)
- 運用益はほぼ期待できない
- 中途解約リスクが大きい
一方、全世界株式への投資であれば、長期的に年4〜6%程度の期待リターンを狙えます。確かに元本保証はありませんが、「時間を味方につける投資」の方が効率的と判断しました。
投資に頼る理由
長期投資ができる
教育費のピークは大学進学時。まだ10年以上先なので、投資の時間的余裕があります。
インフレ対策
教育費や生活費は年々上がる傾向があります。投資で資産を増やしておくことで、インフレにも対応可能。
金融教育の副産物
「親が投資で教育費を準備している」こと自体が、子どもの金融リテラシー教育にもなります。
想定リスクと対策
もちろん、投資にはリスクもあります。
- 大学入学と暴落が重なるリスク
→ 高校3年からは段階的に現金化して安全資産にシフト。 - 課税口座なので税金が発生する
→ 利益には20.315%の税金。教育費は必ず必要になる支出なので、課税分も含めてシミュレーション済み。 - 思ったより早く資金が必要になる場合
→ 現金300万円を別枠で確保して対応。
教育資金の最終プラン(わが家のモデル)
| 項目 | 金額(概算) | 準備手段 |
|---|---|---|
| 小中高の教育費 | 約250万円 | 現金 |
| 突発費・予備費 | 約50万円 | 現金 |
| 大学資金 | 約850万円 | 投資信託(課税口座) |
| 合計 | 約1150万円 | 現金:300万/投資:850万 |
まとめ:教育資金は“分散と時間”で積み立てる
我が家では、現金300万円+投資850万円という二本立てで教育費を準備する計画です。
- 現金は安心のために
- 投資は効率よく増やすために
- 学資保険はコスパが悪いため利用せず
- NISAも使わず、シンプルに課税口座で積立
教育資金は「避けて通れない将来の支出」。だからこそ、時間を味方につけて少しずつ積み立てることが、結局いちばん楽な方法だと思います。
この記事が、同じように教育資金の準備を考えているご家庭の参考になれば幸いです。
積立投資で教育費を運用してみようと思われた方は以下の記事も書いてますので、是非参考にしていただけると幸いです。
【最強のマネーマシン】楽天証券×楽天銀行で資産形成を始めよう
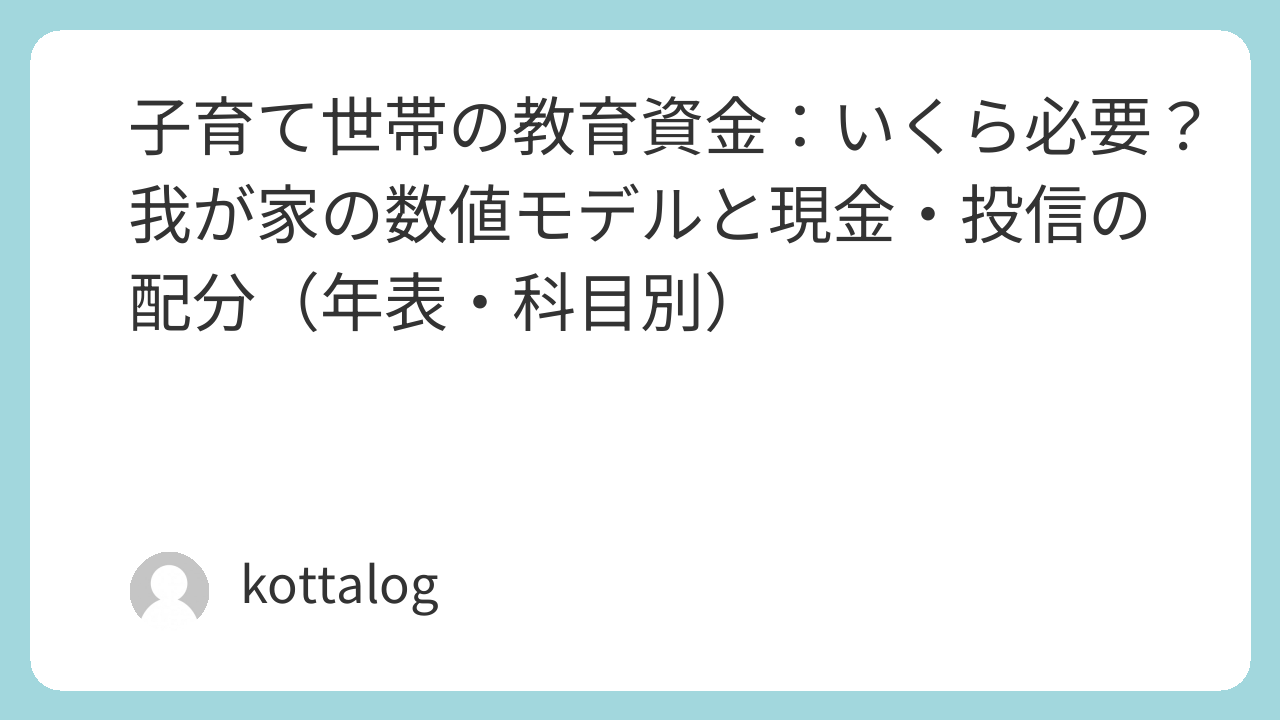
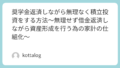
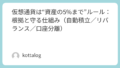
コメント