投資信託を始めてしばらく経つと、必ずぶつかる壁があります。
それは「やめたくなる瞬間」。
最初の数カ月は順調に積み立てが増えて「おお、資産が増えてる!」とテンションも上がるんですよね。
でも、ある日ふとアプリを開いたら真っ赤な数字が並んでいたりして…。
「え、先月プラスだったのにマイナスに? もうやめたほうがいいんじゃないか?」と、不安になってしまう。
これは、投資を始めた誰もが通る道です。私も例外じゃなくて、最初の頃は値動きに振り回されて、何度も売却ボタンを押しそうになりました。
でも結局のところ、長く続けられる人が勝つんですよね。
だから大事なのは「やめない仕組み」を先に作ってしまうこと。
気合とか根性に頼らずとも、仕組みが自動で積み立てを継続してくれる状態を作る。それが投資信託の本当の戦い方なんです。
なぜ「仕組み化」がそんなに大事なのか?
人間は感情に左右される生き物です。
頭では「長期投資こそ王道」とわかっていても、心が「不安だから逃げたい」とささやいてくる。
たとえばダイエット。
「今日はちょっと疲れたから…まぁ明日からでいいか」と思った瞬間に崩れますよね。
投資も同じで、「一旦やめようかな」と思ったときにストップすると、そのまま二度と再開しないことも多いんです。
逆に仕組み化さえしておけば、多少の不安があっても続けられます。
つまり「自分の意志力を信じない」のが正解なんです。
今日からできる「やめない仕組み」の作り方
ここからは実際にどうすればいいのか、具体的な方法を紹介します。
できれば、この記事を読み終わったらすぐに設定してみてください。
① 自動積立を設定する
投資信託を「続ける力」の源は、やっぱり自動積立です。
なぜなら、一度設定してしまえば、翌月からは“勝手に”投資が進んでいくから。意志の力に頼らなくても、仕組みが積み立てを継続させてくれます。
じゃあ具体的にどうやるのか? 例として楽天証券やSBI証券を使う場合の流れを書いてみますね。
ステップ1:毎月いくら積み立てるかを決める
「月3万円」とか「ボーナス月は5万円」みたいに、最初に金額を決めます。
ここで無理をすると続かないので、まずは「ちょっと物足りないかな?」くらいの額がちょうどいいです。
ステップ2:投資信託の商品を選ぶ
積立NISAなら、対象ファンド(全世界株式やS&P500など)から選びます。
最初は「どれがいいんだろう…」と悩むと思いますが、長期で積み立てるなら王道のインデックスファンドで十分です。
ステップ3:積立設定をする
証券会社のサイトやアプリから「積立設定」を選びます。
そこで以下を入力します:
- 毎月の積立金額
- 積立日(給料日直後にしておくと安心)
- 引き落とし口座(給与振込口座か、投資用に分けた口座)
ここで大事なのは「自分で考える余地をなくす」こと。
例えば給料日の翌営業日に設定しておけば、給料が入っても考える前に投資に回されるので、生活費と混ざりません。
ステップ4:ボーナス設定も検討する
もし余裕があれば「年2回のボーナス月だけプラスで積み立て」という設定も可能です。
私も最初は「どうせボーナスは使っちゃうから、強制的に投資へ」と思って組み込みました。結果、ボーナスが入っても気付いたら投資に消えていて、無駄遣いが減りました。
ステップ5:一度設定したら“放置”
ここが最大のポイントです。
自動積立は、設定さえしてしまえば毎月買い付けが実行されます。
だから「今月はやめようかな」と迷うスキがない。正直、最初の設定はちょっと手間なんですが、一度やればあとは放置でOKです。
② 投資用と生活費用の口座を分ける
積立投資が続かない理由のひとつが「生活費と投資資金が混ざっていること」です。
これだと、ちょっと出費がかさんだときに「今月は投資やめておこうかな」と簡単に手を出してしまうんですよね。
だから、最初から 「投資用のお金は触らない」環境 をつくるのがおすすめです。
ステップ1:投資専用の口座を用意する
- 給与振込用のメイン口座とは別に、新しく「投資専用」の口座をつくります。
- たとえば楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行などは、証券会社との連携がスムーズなので便利です。
- 「この口座にあるお金は投資にしか使わない」と決めてしまうのがポイント。
ステップ2:毎月の「仕送り」を自動化する
- メインの給与口座から、毎月決まった額を投資用口座へ自動振込設定します。
- 例えば「毎月25日に5万円を投資用口座へ」といった具合です。
- ネット銀行なら「定額自動振込」の機能があるので、ほぼ手間なしで移動できます。
これをやっておくと「投資に回す/回さない」を自分で判断する必要がなくなり、生活費と完全に切り分けられます。
ステップ3:証券会社の積立と紐づける
- 投資専用口座を、そのまま証券会社の引き落とし口座に設定します。
- そうすると「給与口座 → 投資用口座 → 証券口座 → 自動積立」という流れが完成します。
こうして“自動ベルトコンベア”を作ってしまえば、お金が生活費に紛れません。
実体験:分ける前と後の違い
私も最初は給与口座からそのまま積み立てていました。
するとボーナスの時期になると、「旅行もしたいし、まぁ投資額を減らしてもいいか」と誘惑に負けてしまったんです。
でも証券会社専用の口座を用意して、そこに“仕送り”するようにしてからは、投資資金を生活費に使うことがなくなりました。
生活口座を見ても「今月の残高はこれだけ」と割り切れるし、投資資金は別枠なので安心感が全然違います。
ポイントは、「投資資金を目に入れない」 こと。
③ 相場を見すぎない
投資信託を続けるうえで、最大の敵は「自分の心」です。
アプリを開けば数字が目に飛び込んできて、しかも色は赤や緑で強調されている。人間はそもそも損に敏感な生き物なので、ほんの数%の下落でも「やめようかな」と思ってしまうのは自然な反応なんですよね。
実際、心理学でも「プロスペクト理論」という言葉があって、人は利益の喜びよりも損失の痛みの方を2倍くらい強く感じる、と言われています。
だからこそ“毎日細かく見る”のは、ほとんど拷問に近い習慣なんです。
「毎朝チェックする派」と「極力見ない派」
私は正直に言うと毎朝チェックしています。相場が荒れているときほど気になってしまいますし、もう習慣みたいになっているんですよね。
ただ、ここで重要なのは「自分がどちらのタイプか」を知ることです。
- 気になるタイプ
毎回アプリを開くたびに心が揺れてしまう。下落を見ると落ち込んで、解約ボタンに手が伸びそうになる。
→ この場合は、通知を切って「月1回だけチェック」とルールを作る方が精神的に楽です。 - 気にならないタイプ
見ても「ふーん、下がってるな」くらいで済む。むしろ積み立てを淡々と続けるモチベーションになっている。
→ この場合は毎日見ても問題なし。むしろ「今は安く買えている」とポジティブに捉えられることもあります。
見すぎてしまうと起きること
相場を毎日細かく追いすぎると、次のような落とし穴にハマります。
- 短期目線に偏る
「今日の利益/損失」で判断しがちになり、長期投資の目的を忘れる。 - 余計な売買をしたくなる
「今売っておこう」「別のファンドに乗り換えよう」と、積立投資に不要なアクションをしてしまう。 - 精神的に疲れる
ちょっと下がっただけでモヤモヤする日々が続き、投資そのものが嫌になる。
積立投資の本質は「長期でコツコツ」なのに、日々の値動きに反応してしまうと逆効果なんです。
「見ない仕組み」をつくるには
もしあなたが「見ると不安になるタイプ」なら、次の工夫をしてみてください。
- アプリの通知をすべてオフにする
- 残高を確認するのは「月末の1回だけ」と決める
- 評価額ではなく「積み立てた元本」の合計を見る
私自身も、毎日見ていた頃は「1万円減った」と落ち込む日が続きましたが、月1回のチェックに切り替えてからは驚くほど気持ちが楽になりました。
1カ月単位で見ると、短期的な上下は気にならなくなり、むしろ「積み立て元本がここまで増えたのか」と前向きに感じられるんです。
相場を「毎日見る/見ない」はどちらでもOKです。
大事なのは、自分が 不安に振り回されるタイプかどうか を知って、そのうえで見方を調整すること。
気になるなら見なければいいし、気にならないなら好きなだけ見てもいい。
要は「数字に支配されない工夫」が、やめないための仕組みになるんです。
④ 投資目的を可視化しておく
投資信託をやめたくなる瞬間って、結局「なんでやってるんだっけ?」と目的を見失ったときに訪れます。
相場が下がったり、生活がちょっと苦しくなったりすると、つい「別に今やらなくてもいいか」と思ってしまうんですよね。
だからこそ大切なのが、目的をハッキリさせて目に見える形にすること。
「なんのために積み立てているのか」を自分に繰り返し思い出させる仕組みを作ると、ブレにくくなります。
目的を“書き出す”と強くなる
「老後資金のため」「教育費のため」と頭ではわかっていても、心が不安に負けると忘れてしまいます。
そこで有効なのが、書き出して“見える化”すること。
- ノートに「20年後、子どもの大学費用に300万円」と書く
- スマホのメモに「老後の生活費の安心のため」と記録する
- 付箋に一言だけ書いてPCやデスクに貼る
書いた瞬間は「ちょっと大げさかな」と思うかもしれませんが、下落局面に入ったときに効果を発揮します。
「あ、そうだ。これは“未来のため”にやってるんだった」と自分に言い聞かせられるんです。
長期目標を“数字”に落とし込む
もう一歩踏み込むなら、目的を数字にしてみるのもおすすめです。
- 老後資金:毎月3万円×20年=約720万円+運用益
- 教育資金:月2万円×18年=約430万円+運用益
こうやって「未来にいくら必要で、そのために毎月いくら積み立てる」と数字に落とすと、短期のマイナスはほとんど気にならなくなります。
だって、今日1万円減っても、最終ゴールの700万円にはほとんど影響がないんですから。
視覚的にイメージする
もっとモチベーションを高めたいなら、視覚的に目的をイメージするのも効果的です。
- 「子どもが大学に通っている姿」を想像する
- 「老後に旅行している写真」を壁に貼っておく
- ゴールに近づくイメージを日常で意識する
ちょっと自己啓発っぽいですが、これが意外と効きます。
「今は苦しいけど、未来の自分や家族のため」と思えると、短期的な不安は和らぎます。
実体験:目的を見失ったとき
私も積立を始めたばかりの頃、株価が下がったタイミングで「やめようかな」と何度も思いました。
その時最初に投資を始めた理由や目的を思い出すようにして何とか耐えました。
ポイントは、「目的を忘れない仕組み」を作ること。
書き出す・数字にする・イメージする、方法はなんでもいいんです。
大事なのは、相場が荒れても「このために続けているんだ」とすぐに思い出せること。
それが“やめない自分”を支えてくれるんです。
⑤ 生活費に直結しない額を投資する
積立投資を途中でやめたくなる大きな原因のひとつが、「投資額が生活に食い込んでしまうこと」です。
たとえば、毎月の手取りが25万円の人が「毎月5万円積み立てる!」と気合いで始めたとします。
最初は「よし、未来のために!」と気持ちも盛り上がるんですが、数カ月後に急な出費(冠婚葬祭、家電の買い替え、子どもの学校関連費用など)が重なると…
「いや、今月はちょっと無理だからやめよう」となってしまう。
これでは長続きしません。
投資信託で大事なのは金額の大きさよりも、無理なく続けられる金額をコツコツ積み上げることなんです。
目安は「生活費を引いた余剰資金の2〜3割」
実際の積立額の目安としては、毎月の余剰資金(生活費・固定費・予備費を引いた残り)のおよそ2〜3割くらいがちょうどいいです。
- 手取り25万円
- 生活費・固定費 20万円
- 余剰資金 5万円 → そのうち2万円を積立に回す
- 手取り30万円
- 生活費・固定費 22万円
- 余剰資金 8万円 → そのうち3万円を積立に回す
これくらいだと、突発的な出費があっても積立を止めずに済みます。
最初は「小さすぎるかな?」くらいが正解
人によっては「月1万円なんて少なすぎるのでは?」と不安に思うかもしれません。
でも20年続ければ、1万円×12カ月×20年=240万円。
しかも投資信託は複利で増えていくので、利回り3〜5%なら300万〜400万円以上になる可能性もあります。
逆に「無理して毎月5万円」だと、数年でギブアップしてゼロになってしまうリスクが高い。
だったら少なくてもいいから「続けられる額」で始めた方が、結果的に大きな資産になります。
心理的な余裕が「やめない力」になる
積立額が生活費に食い込んでいると、相場が下がったときに不安が倍増します。
「今月も赤字なのに、投資でも損してる…」と感じたら、そりゃやめたくなりますよね。
でも余裕を持った額なら、「まあ、下がってるけど生活は回るし」と冷静でいられます。
この“心理的な余裕”こそが、やめないための最強の武器になります。
実体験:最初に欲張って失敗した話
私も最初、気合いを入れて「月5万円」を積み立てていました。
でも当時の手取りは23万円くらい。家賃や生活費を払ったらカツカツで、クレジットの請求が来るたびに「どうしよう」と焦っていました。
結果、3カ月目にして「もうやめようかな」となり、積立を一時ストップ…。
その後、月1万円から再スタートしました。
拍子抜けするくらい余裕があり、相場が下がっても「まあ続けていればいいか」と気楽に構えられるようになったんです。
今では「最初から少額でよかった」と心から思っています。
ポイントは、「続けられる額」で始めることに価値がある」 ということ。
大きな額を積み立てるのは、収入が上がったり生活に余裕が出てからで十分です。
最初は「これなら無理なく続けられる」という額に抑えることが、“やめない仕組み”になります。
それでも不安になったときの対処法
どれだけ仕組みを作っても、不安になる瞬間は必ずやってきます。
「こんなに下がって大丈夫なのかな」「やっぱりやめたほうがいいかも」——そんな気持ちになることもあるでしょう。
そんなときに試してほしいのが、歴史を振り返ることです。
過去の株価チャートを見ると、短期的には何度も大きく下がっているのに、長期で見ると右肩上がりなんですよね。
つまり、今の下落も長期で見れば通過点にすぎません。
あとは、同じように積み立てを続けている人のブログやSNSをのぞいてみるのもおすすめです。
「みんな同じように不安なんだな」と分かると、それだけで安心できたりします。
まとめ:仕組み化で「やめない自分」を作る
投資信託をやめないために必要なのは、意志の強さではなく仕組みです。
- 自動積立の設定
- 生活費と投資用の口座を分ける
- 相場を見すぎないルール
- 投資目的を可視化する
- 無理のない金額で始める
この5つを整えるだけで、「やめたい」という衝動をかなり防げます。
投資って、途中でやめたくなるのは“普通”なんです。
だからこそ「やめない工夫」を先にしておくことが、未来の資産を守る一番の方法になります。
読んだだけで終わらせず、今日ちょっとだけでも設定してみてください。
未来の自分がきっと「続けてよかった」と笑っているはずです。
以下の記事も読んでみてください。
【最強のマネーマシン(個人感)】楽天証券×楽天銀行で資産形成を始めよう
マネーブリッジとは?楽天証券×楽天銀行を連携するメリットと設定方法
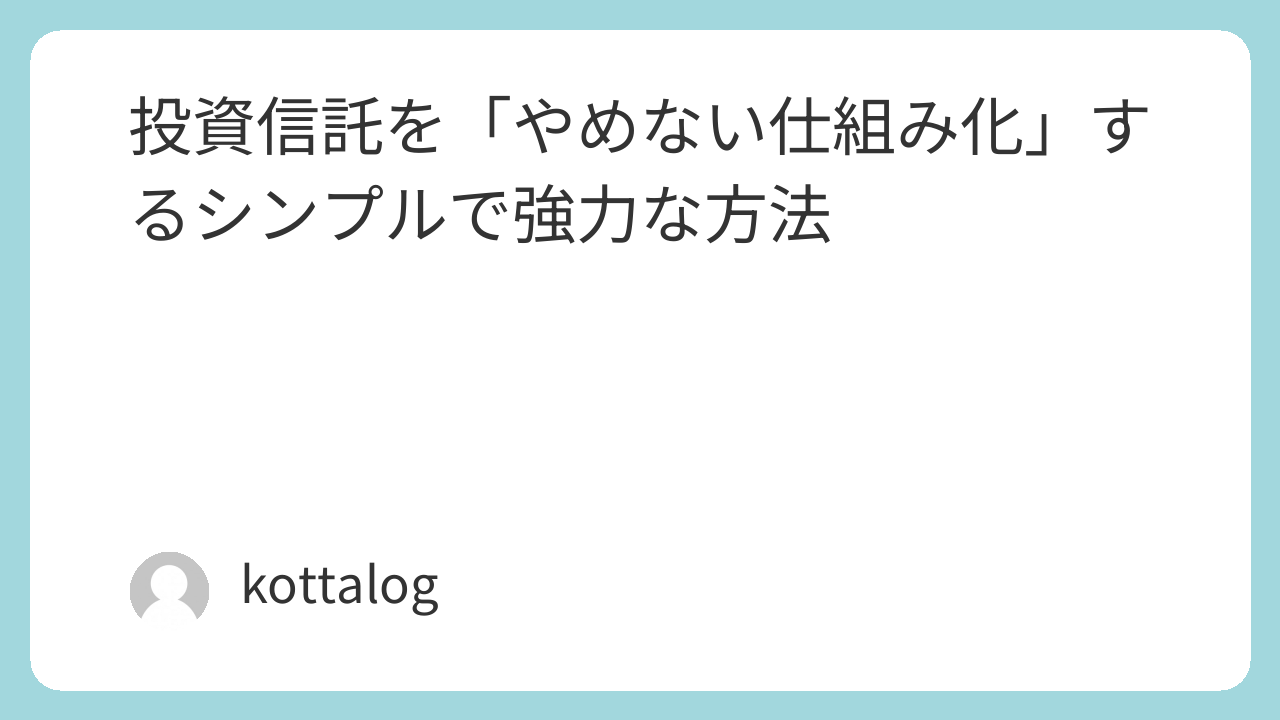
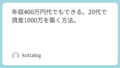
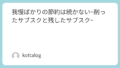
コメント