子育て世代にとって大きなテーマの一つが、「教育費」と「老後資金」のどちらを優先して貯めていくか、という問題です。おそらく多くの家庭で、一度はこの問いに直面するのではないでしょうか。教育費は子どもの将来に直結しますし、老後資金は自分やパートナーの生活の安定に直結します。どちらも軽視することはできません。けれども収入には限りがあり、すべてを同時に完璧に準備するのは現実的には難しいものです。
私自身も子どもが生まれたタイミングでこの課題に直面しました。毎月の生活費や住宅ローンに加えて、教育費と老後資金を両方同時に積み立てるのは、数字上では可能でも心理的にはなかなかのプレッシャーです。何かを優先するという判断を避けたまま、ただ「両方頑張る」と意気込んでも、実際には中途半端になってしまうのが現実でしょう。そこで、我が家ではあえて「優先順位をつける」という方針をとりました。
世の中の多くのマネー本やファイナンシャルプランナーの記事を読んでいると、「老後資金は3,000万円必要」とか「教育費は一人当たり1,000万円以上かかる」といった目安がよく出てきます。それを目にすると、どうしても「全部を早めに用意しなければ」と焦りがちです。しかし、冷静に考えてみれば教育費には“期限”があります。子どもが小学生から高校生、大学生になるまでの20年間ほどで必要な金額が決まっており、その時期を逃せば後から取り戻すことはできません。一方、老後資金はリカバリーの余地があります。子どもが独立した後に支出が減ることで、50代以降に集中して貯め直すこともできますし、退職金や年金という収入の後押しも見込めます。
この違いを踏まえて、我が家では「教育費を優先する」という結論に至りました。ただし、むやみに教育費にお金を投じるのではなく、本人が希望しない習い事や塾には通わせないといった“お金の使い方のルール”も設けています。教育費は子どもの将来を支えるための投資ですが、やる気のない習い事に毎月数万円を払うのは、投資というより浪費になってしまうからです。
結果として、「必要な教育費を逆算して毎月積み立てる」「不足分は奨学金を利用しつつ、実際の返済は親がサポートする」「老後資金は現時点で半分ほど貯まっているので、焦らず子ども独立後に巻き返す」という戦略をとるようになりました。教育費と老後資金の両立は難しいテーマですが、我が家なりの優先順位を決めたことで、資金計画に迷いがなくなり、日々の生活にも安心感が生まれています。
教育費を優先した理由
子どもが生まれると、親として一番に考えるのは「この子にどんな環境を用意してあげられるだろう」ということでした。衣食住の基盤を整えることはもちろんですが、もう少し長い目で見たときに欠かせないのが教育費です。教育にお金をかけることは、子どもの将来の選択肢を増やす投資だと考えています。
お金をどう使うかというのは家庭ごとに考え方が分かれる部分ですが、我が家では迷った末に「教育費を優先する」という方針を決めました。老後の資金も確かに大切です。しかし、老後はある程度の年齢になってからでも取り返しが効く部分があります。例えば50歳を過ぎてからでも、教育費の負担が終われば貯蓄を増やすことはできますし、退職金や年金といった収入の裏付けもあります。一方で、教育費はそうはいきません。子どもが小学生、中学生、高校生、大学生と成長していく「その時期」に必要であり、そのタイミングを逃せば後から用意しても意味がないのです。
教育の機会は一度きりで、やり直しがきかないものです。たとえば大学進学の時に学費が足りなければ、その進学自体を諦めるしかありません。「数年後にお金を用意できたから、もう一度大学を受け直そう」と簡単に言えるほど現実は甘くありません。人生の節目で必要になる教育費は、親が責任を持って準備しておくしかないのです。
また、教育費を優先することは、単に学校に通わせるための資金を確保するという意味だけではありません。子どもが「これを学びたい」と思ったときに、その気持ちを後押ししてあげるための準備でもあります。本人がやる気を持って挑戦したいと言ったとき、費用の心配でそれを断念させるのは、可能性の芽を摘んでしまうようなものだと感じます。子どもの熱意を応援できる環境を整えることこそが、親にできる最大の投資だと思っています。
一方で、教育費といっても無制限にお金をかければ良いとは考えていません。我が家では「本人が希望しない限り習い事や塾には通わせない」というルールを設けています。やる気のない習い事に毎月数万円を払っても、それは投資ではなく浪費です。親の自己満足でお金を使うのではなく、子どもの主体性を尊重することが、結果的に教育費の使い方を健全なものにすると思っています。
老後資金と比べて教育費を優先する理由のもう一つは、時間の制約です。老後資金は「ある程度の時期から取り返すことができる」と書きましたが、これは実際に数字を見ても納得できます。我が家の場合、老後資金は3,000万円程度を目安にしています。すでに1,500万円ほど積み立てができており、残りは50歳を過ぎてから集中的に貯めても十分に追いつけると試算しています。子どもが独立して教育費の負担がなくなれば、その分を老後資金に回せばよい。さらに退職金や年金も加わりますから、ある程度の安心感があります。
ところが教育費はそうはいきません。大学入学のタイミングでまとまった資金が必要ですし、高校でも進学先によっては公立か私立かで大きく金額が変わります。タイムリミットが決まっている以上、老後資金よりも優先度は高くせざるを得ません。教育費は「待ったなし」で、しかも失敗の許されない性質を持っています。だからこそ、我が家では子どもが生まれた段階から必要な金額を逆算し、毎月コツコツと積み立てを始めました。
子どもの未来は、親がどれだけ準備できるかに左右される部分があります。もちろん、親がすべてを肩代わりする必要はないと思っていますし、場合によっては奨学金を借りてもらうことも想定しています。ただ、その場合でも返済は最終的に親がサポートするつもりです。子どもに不必要な負担を残したくないからです。教育費を優先して準備するのは、単に「学校に行かせたい」というだけではなく、子どもが自分の人生を自由に選べる状態にしてあげたいという思いから来ています。
老後資金ももちろん大切ですが、人生のどこで優先順位をつけるかを考えると、私にとって答えは明確でした。老後は自分の努力次第でどうにでもなりますが、子どもの成長は一度きりです。その限られた時間にしっかりと投資することが、最終的に親として一番納得のいくお金の使い方だと感じています。
我が家の教育費ポリシー
教育費を優先する方針を決めたうえで、次に大切なのは「どうやってそのお金を使うか」というルールづくりでした。我が家では大きく3つの考え方を柱にしています。
①本人が希望しない習い事・塾には通わせない
「子どものためになるから」「周りもやっているから」という理由だけで習い事や塾に通わせるのは避けています。やる気がないのに続けても成果は出ませんし、毎月の費用は家計にとって大きな負担になります。習い事は月5,000円から高ければ数万円まで幅広いですが、やる気がないまま数年続ければ数十万円単位のお金が消えてしまいます。それは教育への投資ではなく浪費です。
我が家では「本人がやりたい」と言ったときに、初めて習い事や塾を検討するようにしています。その方が本人も真剣に取り組みますし、支払う側の親としても納得感があります。
②公立高校まで進学、自宅から私立大学に通う前提で試算
教育費の最大の山場は大学進学です。文部科学省や日本政策金融公庫の調査によると、私立大学(文系)の学費は年間約100万円、理系だと年間150万円を超えることもあります。さらに入学金や教材費もかかります。
ただ、すべてを最大値で見積もると不安ばかりが大きくなり、現実的な計画が立てられなくなります。そこで我が家では「高校までは公立」「大学は私立文系に自宅から通う」というシナリオを前提にしました。自宅から通える大学に限定することで、生活費や仕送りが不要になり、必要額は大幅に抑えられます。
参考までに、我が家で試算した金額は以下の通りです。
| 学校区分 | 公立/私立 | 年間費用の目安 | 年数 | 合計金額 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 公立 | 約32万円 | 6年 | 約192万円 |
| 中学校 | 公立 | 約48万円 | 3年 | 約144万円 |
| 高校 | 公立 | 約46万円 | 3年 | 約138万円 |
| 大学(文系) | 私立・自宅通学 | 約100万円 | 4年 | 約400万円 |
| 合計 | – | – | – | 約874万円 |
文部科学省「子供の学習費調査」や私立大学の平均値を参考に、現実的なラインで算出しています。もちろん、部活動や修学旅行など追加費用もあるため、実際には1,000万円弱を見込んでいます。
③必要額を算出し、出産後すぐに積立を開始
子どもが生まれた直後に「必要額=約1,000万円弱」と逆算し、毎月積み立てを始めました。積立額を大きくしすぎると家計が圧迫されますし、小さすぎると将来の不足が怖い。そこで我が家では「18歳までに1,000万円を準備する」という目標を設定し、シンプルに割り算しました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 必要額(目安) | 1,000万円 |
| 積立期間 | 18年(0歳〜18歳) |
| 毎月必要な積立額 | 約46,000円 |
児童手当を教育資金に回す前提で、実際の積立額は月3万円台に抑えることができています。児童手当は総額で約200万円程度になるため、それを教育資金に組み入れるだけで負担は大きく軽減されます。
また、積立方法はシンプルに投資信託の積立を利用しています。銀行の普通預金に置いておくだけではインフレに負けてしまうため、つみたてNISAを活用して全世界株式に分散投資。長期で運用することで、教育費の積立でもリスクを抑えながら増やすことを目指しています。
不足分の対応策
どれだけ計画的に積み立てをしていても、人生は想定通りにいかないものです。教育費に関しても同じで、子どもが希望する進路や物価上昇など、当初のシナリオを超える出費が発生する可能性は十分にあります。特に大学進学では、学部の選び方や研究費、留学などで金額が跳ね上がるケースも珍しくありません。そうした「予想外の支出」にどう備えるかは、教育資金計画における大事なポイントです。
我が家の場合、基本的な教育費は出産直後から積み立てを始め、18年間で約1,000万円を準備する計画を立てています。ただし、それで全てがまかなえるとは考えていません。将来、子どもが私立理系や芸術系の学部に進学する可能性もありますし、留学を希望するかもしれません。そのときに積み立て額だけでは不足するかもしれない。そうした想定外に対する「セーフティーネット」として、奨学金の活用を視野に入れています。
奨学金は「最後の保険」として位置づける
奨学金というと、「借金だからできれば避けたい」と考える人も少なくありません。確かに無計画に利用すると、社会人になってから長期間返済に追われ、生活の足かせになるリスクもあります。ですが、日本学生支援機構(JASSO)の第一種奨学金のように無利子で借りられる制度も存在しますし、返済も卒業後から始まるため、仕組みとしては非常に使いやすい制度です。
我が家では「教育費の不足分を埋めるための最後の保険」として奨学金を位置づけています。つまり、まずは積み立てと児童手当でできる限り準備し、それでも不足したときに初めて活用する。安易に借りるのではなく、あくまで将来の選択肢を広げるための手段です。
子ども名義で借り、親が返済をサポートする
ただし、借りるのは子ども自身です。奨学金はあくまで「子どもが受ける教育のための資金」なので、名義も子どもにするのが自然です。しかし、返済については原則として親が肩代わりするつもりです。
理由はシンプルで、子どもに負担を残したくないからです。奨学金を自分で返していくのは社会人としての責任感を育むという見方もありますが、我が家の考え方は少し違います。若いうちに本来なら自己投資や経験に使えるお金を、奨学金の返済に充てるのはもったいないと感じるのです。社会人になったばかりの数年間は、収入もまだ高くなく、生活の基盤を整えるのに精一杯の時期です。その時期に月1〜2万円の返済が重なると、結婚資金や資格取得、留学といった新しい挑戦が制限されてしまいます。
教育費を優先して積み立てているのは、子どもが自由に未来を選べるようにするためです。奨学金の返済が重荷になって可能性を狭めてしまっては本末転倒だと考えています。そのため、不足分が出た場合はいったん奨学金を利用しても、実際の返済は親が肩代わりし、子どもが社会に出た後の負担を軽くする方針にしています。
「子どもの選択肢を狭めない」ことが最優先
不足分の対応策を考えるとき、一番大事にしているのは「子どもの選択肢を狭めない」ということです。経済的な理由で夢を諦めざるを得ないというのは、親としては避けたいシナリオです。もちろん、限界はあります。例えば海外の大学にフル留学したいと言われれば、何千万円もの費用が必要になるかもしれません。それをすべて親が負担するのは現実的ではありません。しかし、少なくとも「やりたい」と言ったときに「お金がないから無理」と突き放すのではなく、どう工夫すれば実現できるかを一緒に考えたい。そのときに奨学金は大きな助けになります。
また、奨学金を利用した場合でも、「子どもに返済義務が残るのは事実」という点はしっかり伝えるつもりです。そのうえで「親が返済をサポートする」と約束する形を取ります。これは単なる金銭的なサポートではなく、「親が一緒に背負うから安心して挑戦していい」というメッセージでもあります。
数字で見た奨学金利用のシナリオ
実際に我が家が考えているシナリオを簡単に試算すると、以下のようになります。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 教育費総額(公立高+私立大文系・自宅通学) | 約1,000万円 |
| 積立+児童手当で準備できる額 | 約800万円 |
| 不足分 | 約200万円 |
| 奨学金利用(第一種・無利子) | 月額5万円 × 4年 = 240万円 |
| 返済計画 | 卒業後15年で返済(毎月約13,000円)※後々私達親が負担予定 |
このように、不足分が出た場合でも、無利子の奨学金を利用すれば現実的な範囲でカバーできます。そして返済は私達親が計画的に行うことで、子どもの社会人生活に負担を残さないようにする。こうしたシナリオを持っているだけでも、「足りなかったらどうしよう」という不安がぐっと軽くなります。
老後資金の考え方
教育費と並んで、多くの家庭にとって大きな関心事となるのが老後資金です。金融庁が数年前に発表した「老後2,000万円問題」が話題になったことも記憶に新しいですが、実際に老後に必要とされる資金は約3,000万円とも言われています。もちろん家庭のライフスタイルや住まいの状況、年金受給額によって必要額は変わりますが、一つの目安としてこの数字は広く浸透しているように感じます。
私自身も「老後にいくら必要なのか」を真剣に考えた時期がありました。そして教育費との兼ね合いを整理してみると、「今の時点で老後資金を最優先に積み立てる必要はない」という結論にたどり着きました。すでに1,500万円ほどの資産があり、これは一般的な家庭と比べてもある程度の安心材料になっています。もちろん、3,000万円に達していないので油断はできませんが、子どもがまだ小さい今の段階で無理に老後資金を積み上げるより、教育費を優先する方が理にかなっていると考えています。
すでに半分は確保できている安心感
現時点で1,500万円を準備できていることは大きな安心材料です。仮にこの資金を投資信託や株式などで運用し、年率3〜4%で運用できれば、20年後には複利効果で倍近くになる可能性もあります。つまり、追加で積み立てを行わなくても、ある程度は自然に増えていくという見通しがあります。もちろん投資にリスクはつきものですが、インフレや低金利を考えると、現金で寝かせておくよりも運用を組み合わせる方が現実的です。
老後資金は「いま全額を揃えておかなくてはいけない」ものではなく、「子どもが独立した後に巻き返せる」というのが私の考えです。この発想にたどり着いたことで、教育費を優先しても罪悪感を持たずに済むようになりました。
教育費が不要になる50歳以降が勝負
老後資金の最大の特徴は、「取り返しがきく」点にあります。教育費と違い、支出のタイムリミットがないのです。子どもが独立すれば、それまで毎月数万円単位で積み立てていた教育費分をそのまま老後資金にスライドできます。例えば月5万円を10年間積み立てれば、それだけで600万円になります。さらにボーナスや余裕資金を加えれば、1,000万円近く積み増すことも十分に可能です。
また、退職金という大きな収入も老後資金を支える重要な柱になります。企業によって差はあるものの、平均すると大企業では2,000万円前後、中小企業でも1,000万円弱の退職金が支給されるというデータがあります。仮に我が家が平均的な水準を受け取れるとすれば、退職金と積み立てを合わせることで、老後資金3,000万円という目標は十分に射程圏内に入る計算です。
老後の生活費を冷静に見積もる
「老後に3,000万円必要」とよく言われますが、この数字を鵜呑みにする必要はないと思っています。なぜなら、実際に必要な金額は生活のスタイルや環境によって大きく変わるからです。もし、持ち家で住宅ローンが完済していれば、家賃や住居費はほとんどかかりません。車を持たず公共交通機関を利用すれば、維持費も大幅に削減できます。
総務省の家計調査によると、夫婦二人の平均的な生活費は月26万円程度とされています。これにゆとりのある暮らしを加えて月30万円と見積もっても、年360万円。年金収入が月20万円あれば、不足分は年間120万円。これを30年間カバーすると3,600万円になります。確かに大きな額ですが、年金額や退職金の有無によって実際に必要な「自助努力分」はかなり圧縮できるのです。
「今は教育費、老後は後から」が自然な流れ
教育費と老後資金を両立しようとすると、どうしても「今の生活費を削ってまで貯めなければ」というプレッシャーが強くなります。しかし、教育費には期限があり、老後資金にはリカバリーの余地がある。この違いを踏まえれば、若いうちは教育費を優先し、子どもが独立してから老後資金を本格的に積み立てる方が自然な流れだと思います。
実際、我が家では50歳以降に教育費が不要になる見込みなので、そのタイミングで毎月5〜10万円を老後資金に回す計画です。10年間で1,000万円以上を積み増し、退職金と合わせて目標額を達成するシナリオを描いています。現時点で半分の1,500万円が確保できているので、過度な心配をせずに済んでいるのが正直なところです。
まとめ
教育費と老後資金のどちらを優先するかという問いに、我が家なりの答えを出すまでにはそれなりに時間がかかりました。両方とも大切で、どちらも軽視することはできないテーマだからです。子どもの教育費は「その時期にしか使えない」お金であり、タイムリミットが決まっています。一方で老後資金は、子どもが独立した後からでも巻き返す余地がある。両者を比べたとき、我が家は迷わず「教育費を優先する」という方針を取りました。
ただし「教育費優先」とはいっても、無制限にお金をかけるわけではありません。本人が希望しない習い事や塾には通わせないというルールを決め、教育費は“投資”として意味がある部分にだけ使うように心がけています。そのために、公立高校まで進学し、自宅から私立大学に通うという現実的なシナリオを前提に必要額を算出しました。そして子どもが生まれた直後から逆算して積立を開始し、児童手当も含めて計画的に準備しています。教育費は「やればやるほど安心」というものではなく、「必要な分をきちんと積み立てておけばいい」と割り切ることが、結果的に家計の健全性を守ることにつながっています。
一方、老後資金については「今すぐに全額をそろえる必要はない」という考え方に落ち着きました。一般的に必要とされる3,000万円のうち、すでに1,500万円ほどを準備できているため、切迫感はありません。さらに、子どもが独立した後は教育費の負担がなくなり、その分を老後資金に充てられる。50歳以降の10年間で集中的に積立を行い、退職金と合わせれば十分に目標額に届くと考えています。つまり「老後資金は後からでも取り戻せる」という安心感をベースにしているのです。
教育費と老後資金の両立は簡単ではありません。しかし、優先順位を明確にし、無駄を省き、必要な部分にだけ計画的にお金を投じることで、不安は大きく減ります。我が家にとっての結論は「教育費優先、老後資金は後から」。この方針を定めたことで、毎月の家計管理に迷いがなくなり、将来への見通しも立てやすくなりました。大切なのは、完璧に両立させることではなく、自分たちに合った優先順位を見つけて実行することだと思っています。
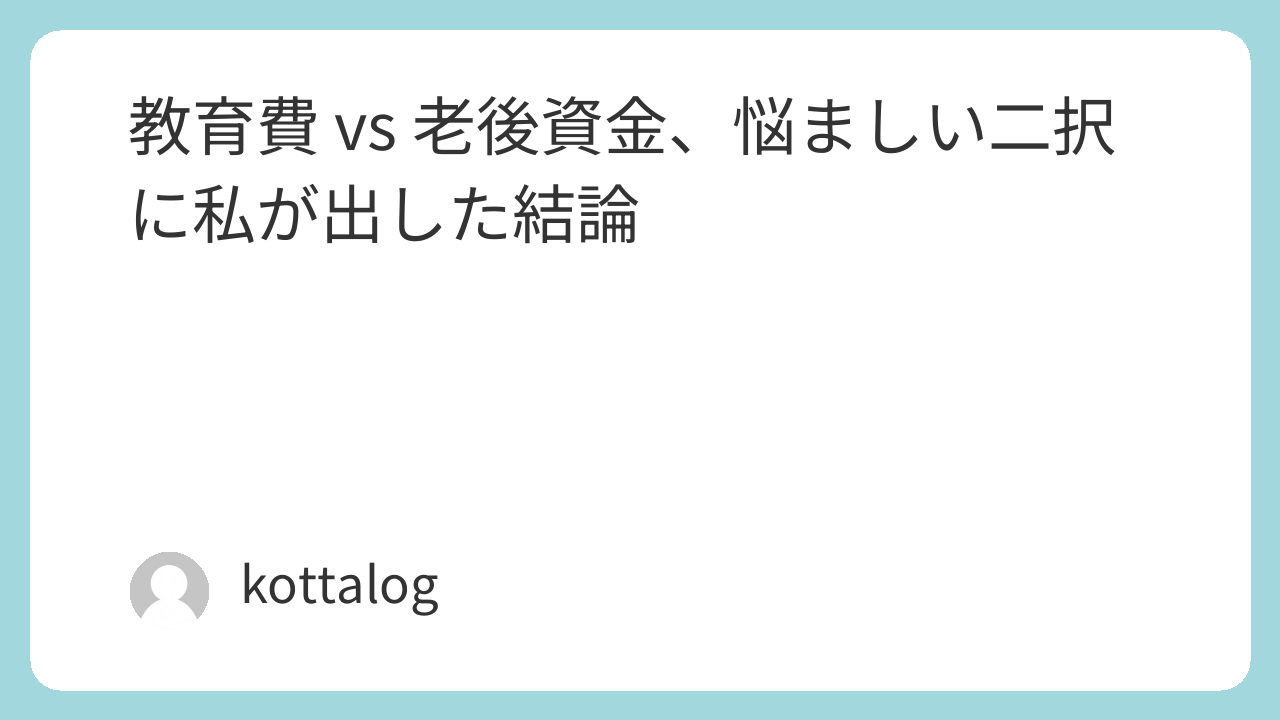
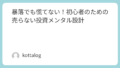
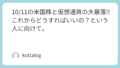
コメント