10/11に何が起きたのか:米国株と仮想通貨の急落
2025年10月11日、この日は世界のリスク資産市場にとってショッキングな一日となりました。米国株式市場、仮想通貨市場、そして日本の先物市場までが同時多発的に大きな下落を記録し、投資家心理に大きな衝撃を与えました。ここでは、時間軸を追いながら、何が要因となり、どのように市場が動いたのかを冷静に整理します。
米国株:利益確定売りと対中関税強化懸念が引き金に
10月10日、トランプ前大統領が中国からの輸入品全体に100%の追加関税を課す可能性を示唆する発言をしたことが引き金となり、10月10日のニューヨーク市場では、S&P 500が前日比-2.7%、ダウ平均が-1.9%、ナスダックは-3.6%といった大幅な下落を記録しました。これは4月以来の大きな下落幅とされています。
その流れを引き継ぎ、10月11日の早朝・時間外取引でも先物が急落。日本時間の夜間セッションから先物市場に売り圧力が強まり、地理的時間差を跨いで連鎖反応が始まりました。
11日未明の時点では、ニューヨーク株式市場も引き続き軟調推移を見せ、ダウ平均は時間帯によっては一時500ドルを超える下落幅を示したとの報もあります。このような流れは、先に触れた関税強化懸念が市場のセンチメントを大きく揺さぶったことを示しています。
仮想通貨市場:BTC・ETHで二桁下落、流動性ショックも絡む
仮想通貨市場にも大きな影響がありました。
ビットコイン(BTC)は10月11日には前日比で約 -8.13% の下落を記録し、イーサリアム(ETH)も前日比で -12.94% の急落をしました。
今回の下落には、トランプ氏の関税発言によるリスクオフの流れが引き金になったとの見方が強く、株式市場との連動性が改めて浮き彫りになりました。
また、仮想通貨市場内でもレバレッジポジションの清算(いわゆるロスカット)や、大口ポジションの担保切れ売りがスパイラル的に売りを連鎖させた可能性が指摘されています。
こうした流動性ショックは、一過性の暴落として作用しやすい特性を持ちます。
特筆すべきは、仮想通貨全体の時価総額も深く影響を受けたこと。10月11日時点で暗号資産市場の時価総額は約 633.49兆円 にまで膨らんでいましたが、24時間売買代金も32.39兆円という大きな取引が発生しており、売買のボラティリティが非常に高まっていたと見られます。
つまり、この日は「急落」と「売りの連鎖」が複合的に重なった、非常に激しい市場ショックだったのです。
日本・日経先物への波及:週明け大幅下落の布石か
米国株、仮想通貨といったグローバルリスク資産の急落は、日本市場にもじわじわと波及しました。特に注目すべきは、日経225先物の動きです。
報道によれば、10月11日深夜時点で日経225先物は -1,190円安 の水準で推移しており、これは日本時間の朝方の株価下落圧力を強める値動きと解釈できます。
先物ベースでの大幅下落は、投資家心理として「週明けの日本株もクラッシュ(暴落)的な下落が起こるかもしれない」という懸念を誘発します。特に、三連休明けというタイミングに重なるため、ギャップダウン(寄付きから大幅安スタート)リスクも否めません。
なお、日経先物が急落しても、実際の現物株式市場と先物市場との乖離が必ずしも一致するわけではない点には注意が必要です。しかし、先物の急変動は市場心理を先取りする側面を持つため、無視はできません。
なぜこの急落が起きたのか:要因の整理
この日の急落を引き起こした要因を、複数の視点から整理しておきます。
- 対中関税強化の示唆
トランプ氏の発言がショックとなり、輸出・サプライチェーン依存度の高い銘柄を中心に売りが広がりました。 - 利益確定売り
年初〜中盤にかけて上昇してきた銘柄を中心に、投資家が利益を確定させる動きが加速。特にマーケットが不安定になり始めた局面で、売り圧力を増幅させたと考えられます。 - 流動性ショック/レバレッジ清算
仮想通貨市場では、レバレッジを効かせたポジションが担保切れとなり、強制決済が連鎖的に発生。これが売りを売りを呼ぶスパイラルを助長しました。 - リスクオフ心理の急拡大
世界的に地政学リスク、不透明感の高まりなどが背景となり、安全資産への逃避(キャッシュ移動、債券・金などへのシフト)が強まりました。 - 時間差の輸送・連鎖反応
米国市場での動揺が先行していたため、そのセンチメントが先物・仮想通貨を通じて他市場へ波及。時間的なラグを伴って、日本やアジア市場にも影響が広がった形です。
個人投資家としての実体験:ETH評価額が約11万円減少
今回の急落は、チャートの中だけの話ではありません。私自身の資産にも、しっかりと数字として現れています。2025年10月11日時点で、保有しているイーサリアム(ETH)の評価額は 861,198円 から 742,847円 に下落し、約11万8,000円のマイナス となりました。
数字で見る下落の実感
私のポートフォリオの中で、仮想通貨(ETH)は全体の約5%を占めています。構成比としては小さいものの、やはりボラティリティ(変動幅)が大きいだけに、動きは派手です。
10月10日の夜、いつものようにマネーフォワードMEのアプリを開くと、ETHの価格が一気に滑り落ちていました。前日まで約1ETH約66万円だったのですが、朝起きてみると約55万円になってました。日本円ベースの評価額にして約11万円の下落です。数値を目で追っていくうちに「また来たか」という感覚がよみがえりました。
ただ、ここで特筆すべきは「驚き」よりも「慣れ」です。2021年、2022年の仮想通貨バブルの崩壊を経て、私は何度もこの“ジェットコースター”を体験してきました。むしろ今回の下落は、過去の暴落に比べれば穏やかとすら感じます。とはいえ、数字で見る損失はやはり重みがあります。マイナス11万円というのは、月の生活費に匹敵する金額。冷静さを保つのは簡単ではありません。
インデックスファンドの下落も覚悟
今回の急落は金曜日の米国市場をきっかけに起きたため、日本の土曜日は株式市場が閉まっていました。つまり、私が保有しているインデックスファンドの基準価額はまだ更新されていません。
そのため、正確にどれほど資産全体が減っているのかは、週明けにならないとわかりません。ですが、為替と先物の動きを見れば、おおよその影響は想像できます。おそらく、全世界株式(オルカン)や先進国株式も週明けにかけてそれなりに下がるでしょう。
この「まだ反映されていない時間」が、意外とメンタルに効きます。数字として確定していないだけに、想像が先走ってしまうのです。
それでも私は、週末に慌てて売ることはしません。マーケットが開いていない時間に焦っても何もできないし、これまでも「暴落=買い時」という経験を積んできたからです。
ETHが下がった理由を、冷静に見る
感情的に「下がった」と受け止めるだけではなく、なぜ下がったのかを理解しておくことは重要です。
今回のETHの急落は、米国株の下落に引きずられた面が大きいです。トランプ氏の発言による関税懸念がリスクオフの流れを生み、株式市場の資金が引き上げられた。仮想通貨は“リスク資産の中のリスク資産”として位置づけられているため、資金の逃避先から真っ先に切られた形です。
一方で、ETHそのもののファンダメンタル(基礎的な価値)が崩れたわけではありません。ネットワークの稼働状況や開発進捗、ステーキング報酬率などに異常はなく、ブロックチェーン自体は平常運転です。
つまり「市場心理による下げ」であって、「技術的・構造的な崩壊」ではない。私はそこを冷静に見ています。
「損した」ではなく「割安になった」
損失を数字で見ると、どうしても「減った」「マイナス」という言葉が浮かびます。しかし、長期投資家の視点で言えば、それは「価格が下がった」=「割安になった」ということでもあります。
私がETHを購入している理由は、投機ではなく、分散投資の一環としての「将来性への期待」です。
ブロックチェーン技術が社会インフラとして定着する可能性、AI・金融・ゲームなどへの応用が進む未来に賭けています。その前提が崩れていない以上、価格の上下で判断するのは短絡的だと考えています。
むしろ、こうした暴落局面は、次の積立ポイントを見直す良い機会です。これまでETHはポートフォリオの5%を上限にしていましたが、もし次のボーナス時に余力があれば、買い増しを検討しても良いかもしれません。
(ただし、これは私個人の方針であり、推奨ではありません。自分のリスク許容度に合わせることが大前提です。)
同じように落ち込んでいる人へ
SNSや掲示板を見ていると、今回の下落で大きく動揺している個人投資家も少なくありません。
ネガティブな投稿が多く、過去の暴落時と同じ空気が広がっています。けれど、こういうときに思い出すのは、2018年の仮想通貨冬の時代、そして2020年のコロナショック後の回復です。
市場はいつも、悲観の中で底を打ち、誰もが諦めた頃に上昇します。
私も今回は約11万円減りました。しかし、それは“確定損”ではなく“含み損”に過ぎません。
この含み損は、長期投資の中で必ず通る通過点。これを恐れていたら、資産形成は続けられません。
週明けの日経平均も大幅下落か:連鎖の可能性
10月11日の米国株・仮想通貨市場の急落を受けて、次に焦点となるのは日本株市場、特に日経平均がどこまで影響を受けるかという点です。
日経先物の急落が示す警戒シグナル
10月10日の日本時間深夜〜早朝にかけて、日経平均先物が1,100円超の下落を記録したとの報道があります。
これは前夜の報道(公明党の連立離脱方針など政治的不透明性の拡大)をきっかけとしたものとされており、国内の政局リスクも売り材料として意識され始めています。
さらに、様々なメディアでも「日経先物大幅安」「東京市場、連休明け大荒れか」といった見出しが出ています。
こうした先物市場の動きは、実際の現物取引開始前に市場心理を先取りしており、寄り付きでのギャップダウン(大幅安スタート)の可能性を示唆しています。
国内・海外要因が複合して下落圧力を強める構造
日経平均に下落圧力を与えそうな要因を、主なものから整理しておきます:
- 米中対立再燃・関税懸念
米国発の関税強化示唆がリスクオフの流れを生んでおり、日本株もその影響圏にあります。米国株式市場の重荷がそのまま日本株に波及しやすい局面です。 - 政治不透明性・政局リスク
公明党の連立離脱報道が市場の警戒材料となっています。政権運営に支障を来す可能性があるとの見方が広まり、国内投資家にも慎重姿勢を促しているようです。 - 利益確定売りと過熱感調整
9月・10月上旬に急上昇した高値圏で、買われすぎを意識した利益確定売りの動きが強まりやすいです。特に海外投資家のポジション調整売りが重しになる可能性も高い。 - 金利・為替変動
米国長期金利の上昇、円高の進行なども、株式市場にとっては逆風材料。輸入コスト高や企業収益圧迫の懸念を通じて、景況感悪化要因にもなり得ます。
こうした複数要因が重なれば、「米国株の下落 → 日本先物・株式への連鎖 → 政治・金利要因」で下落圧力が掛かる構図が見えます。
来週予想レンジとリスクシナリオ
複数の証券・メディアが、来週の日経平均の予想レンジを 47,000円〜49,500円 程度と見ています。
上限の近辺で買われ過ぎ感も出ていたため、下振れ余地の方がやや大きいという見方が多いようです。
具体的に発生し得る下落シナリオとしては:
- 寄り付きからギャップダウン
先物の急落が先行しているため、東京市場の始まりで大きく値を下げて始まる可能性が高い。 - 途中下落の流れを引きずる展開
寄り付き後に巻き返しがあっても、午前中から中盤にかけて売り圧力が強まり、下値を切り下げる展開。 - リバウンドの可能性も残る
ただし日中のどこかで「押し目買い」勢力も動きやすく、過度に売り込まれたところでは戻しも期待できる。ただし、全体的な地合いが弱ければ反発幅は限定的にとどまる見込み。
こうしたシナリオを念頭に置きつつ、市場の動きに柔軟に対応することが求められます。
注意点:過度な悲観は禁物、逆に油断も禁物
この見通しはあくまで「可能性」にすぎません。市場は予測通りには動かないことも多く、ネガティブ材料を織り込み切れないこともあります。
また、先物の下落がどこまで現物株価に反映されるかは、参加者の心理と需給に左右されます。流動性が薄い銘柄や中小株は過度に動くこともあり得ます。
一方で、過度に悲観的になる必要もありません。今回の暴落が一時的なショックである可能性、あるいは押し目買いの入りやすさを残す可能性も視野に置くべきです。後続章では、どういう戦略を取るかを前向きに示していきます。
結論:焦って売らず、むしろ買い増す
暴落が起こるたびに、人は「どうすればいいのか」と自問します。
ですが、結論はシンプルです。
「売らない」「焦らない」「買い増す」——この3つに尽きます。
相場が荒れたときほど、冷静でいる人が最後に笑います。感情に流されず、データと歴史を味方につけて動く。それが長期投資の本質です。
「売らない」——長期投資の最大の武器は「保有」
暴落時に最もやってはいけない行動が、恐怖に任せた売却です。
一時的な下落を「損失」と錯覚して売ってしまうと、資産形成のサイクルは途切れます。
逆に、暴落の中でも持ち続けた人だけが、回復の恩恵をすべて受け取ることができます。
たとえば、2008年のリーマンショック。
S&P500はピークから半値以下に下がりましたが、5年後には完全に回復しています。
もし当時、恐怖心で投資信託を売った人は、その後の上昇を逃しました。
一方で、口数を減らさずに持ち続けた人は、分配金と株価回復の両方で報われています。
同じことは、2020年のコロナショックでも起きました。
世界経済が停止し、株式市場は1か月で30%近く下落しました。
しかし、半年後には株価がV字回復。
このときも、「売らなかった人」だけが恩恵を受けています。
市場の下落は一時的ですが、「売ってしまうこと」は永続的です。
長期投資家にとって最大の敵は、マーケットではなく自分の感情です。
「焦らない」——時間を味方にする
暴落時に不安になるのは当然です。
評価額が減ると、頭では「長期目線で大丈夫」と分かっていても、心が追いつきません。
しかし、焦ることこそ損失の源になります。
投資信託や株式の本質的価値は、1日や1週間で変わるものではありません。
企業の利益や経済成長は、数年単位で積み上がっていくものです。
それを1日のニュースや為替変動で判断してしまうと、短期投機と変わらなくなります。
焦らないために私が意識しているのは、「長期チャートを見る」こと。
1か月単位の動きではなく、5年・10年のスパンで見ると、ほとんどの暴落は“わずかな谷”に過ぎません。
長期的に見れば、世界経済はずっと右肩上がりで成長しています。
人口、技術、消費、企業の利益——それらが積み上がる限り、株式市場もやがて戻ります。
焦りを鎮めるもう一つの方法は、「買付設定を止めない」ことです。
積立NISAやiDeCoのように自動積立を続けていれば、相場が下がったときに多くの口数を買うことができます。
これは、いわゆるドル・コスト平均法の力です。
一見「損している」ように見えるときこそ、将来の利益を生む“仕込み期間”になっています。
「買い増す」——暴落はバーゲンセール
投資の世界では、「恐怖の中にこそチャンスがある」という格言がいくつも存在します。
- 「他人が恐れているときに貪欲になれ」——ウォーレン・バフェット
- 「市場は短期的には投票機、長期的には計量機」——ベンジャミン・グレアム
(短期的には人気投票(感情)で株価が決まるが、長期的には企業の実力(利益・価値)が反映されるという意味。)
いずれも、感情ではなく原則で動くことの大切さを示しています。
今のような暴落局面は、将来から見れば“バーゲンセール”です。
優良な投資信託やインデックスが安く買える機会。
暴落を「危機」と見るか、「割安」と見るかで、5年後の資産額は大きく変わります。
私自身も、こうした局面では「買い増し」を検討します。
もちろん、無理にタイミングを当てるわけではなく、余剰資金の範囲で。
特に年末のボーナス時期に合わせて、債券や金など守りの資産を少し崩し、
全世界株式(オルカン)やETHを追加購入する予定です。
暴落で売られているときほど、長期的リターンの源泉は増えます。
「安いときに買って、忘れる」——結局、これが最も堅実な戦略です。
投資を続けた人が最終的に勝つ
金融庁の長期調査によると、20年以上インデックス投資を続けた人の損失率はゼロに近いとされています。
逆に、短期的に売買を繰り返すほど、平均リターンは低下します。
つまり、勝つのは「売買が上手い人」ではなく、「やめない人」です。
暴落を経験したすべての長期投資家が口をそろえて言うのは、
「持ち続けて良かった」「あのとき売らなくて良かった」という言葉です。
そしてその感想は、暴落の“渦中”ではなく、“数年後”にしか得られません。
今の下落が、将来の成長への入口かもしれない。
そう考えるだけで、少しだけ不安は小さくなります。
以下、第7章「まとめ:短期の痛みを長期の利益に変える」を約2000字で執筆しました。
記事全体を振り返りながら、落ち着いた筆致で「長期的視点」と「希望」を結びにしています。
まとめ:短期の痛みを長期の利益に変える
2025年10月11日の大暴落は、投資家にとって久々に心をざわつかせる出来事でした。
米国株、仮想通貨、そして日経先物までが一斉に下がり、「これからどうなるのか」という不安が一気に広がりました。
しかし、ここまで読み進めてきた方ならもう分かると思います。
このような下落は、終わりではなく通過点です。
暴落は“危機”ではなく、“機会”でもあります。
暴落は「短期の痛み」に過ぎない
投資をしている以上、下落は避けられません。
問題は「なぜ下がったか」ではなく、「そのとき自分がどう行動するか」です。
暴落時には、評価額が急減し、数字だけを見れば確かに痛みを感じます。
私自身も、イーサリアム(ETH)の評価額が一夜で約11万円減りました。
ただし、その痛みは短期的なものです。
なぜなら、資産の価値はマーケットの気分で上下する一方、
その裏にある企業・技術・経済の“実体”は一晩で消えるものではないからです。
下がることもあれば、やがて戻ることもある。
歴史的に見ても、どの暴落も時間が経てば「ただの谷」でした。
2008年のリーマンショックでさえ、S&P500は5年で回復しました。
2020年のコロナショックでは、半年後に史上最高値を更新しています。
あのときの暴落を「チャンス」と見た人は利益を得て、
「終わり」と見た人はその後の上昇を逃しました。
暴落は一時の嵐。
長期の投資家にとっては、通り過ぎる雨にすぎません。
ホールド+買い増し=長期の利益
資産形成において最も重要なのは、「売らないこと」です。
そして次に大切なのが、「下がったときにこそ買うこと」。
この2つを組み合わせると、複利の効果が最大化されます。
下落時に売ってしまえば、元本が減り、回復の波に乗れません。
一方で、暴落時に積立や買い増しを続ければ、安く多くの口数を買うことができます。
これが、長期的にリターンを押し上げる最も単純かつ強力な方法です。
たとえば、世界株インデックスを毎月一定額積み立てている場合、
相場が下がった月は「いつもより多く買えている」ということです。
それが数年後、価格が戻ったときに大きな利益として現れます。
ドル・コスト平均法とは、まさに暴落時に真価を発揮する仕組みです。
さらに、暴落時に恐怖で止めてしまう人が多いからこそ、
市場全体の価格は下がり、冷静な人にとっては“チャンスの期間”になります。
つまり、他人の恐怖が、自分の利益の源泉になるわけです。
投資とは「時間との協調」である
投資は、タイミングを読むゲームではありません。
「どの資産を、どのくらいの期間、持ち続けられるか」という時間との協調です。
たとえば、短期で10%下がっても、10年後にはそれが誤差にしか見えないこともあります。
時間を味方につければ、一時の下落も意味が変わります。
暴落は「痛み」ではなく、「未来への割安な入口」になります。
私たちは、将来の自分に“いい買い物をした”と言ってもらうために、今の不安を耐える。
「今はまだ報われなくても、長期的にはプラスになる」と信じることが、長期投資家の強さです。
「あのとき買ってよかった」と思える日のために
私が好きな言葉があります。
「マーケットは短期的に感情で動くが、長期的には現実で動く」。
これは、感情がどれほど強く市場を揺らしても、
最終的には企業の利益、経済の拡大、技術の進化が株価を押し上げるという意味です。
暴落が起きた瞬間は、誰もが不安になります。
「もう投資なんてやめようかな」と思う人も出てくるでしょう。
でも、過去のチャートを見ればわかる通り、
その“やめたくなった瞬間”こそが、最も割安だった瞬間です。
もし5年後、10年後の自分が今日を振り返ったとき、
「あのとき勇気を出して買っておいてよかった」と思えるなら、
この一時の痛みは、意味のある経験になります。
そのとき、今日の下落は「損失」ではなく「投資」だったと気づくはずです。
投資における最善の行動は「続けること」
どんなに優れた銘柄を選んでも、途中でやめてしまえば意味がありません。
積立を止めず、買付を継続し、暴落にも動じないこと——
それが最終的に資産を築く唯一の方法です。
金融庁のデータでも、20年以上の積立を続けた投資家は、ほぼ全員がプラスになっています。
一方で、短期で売買を繰り返した人ほど、マイナスに終わる傾向があります。
投資の勝敗は「センス」ではなく、「継続力」で決まるのです。
未来へのメッセージ
市場が荒れている今だからこそ、皆さんにあえて言いたい言葉があります。
「暴落はバーゲンセール。」
下がっている今こそ、未来に向けた仕込みをする絶好のタイミングです。
焦らず、売らず、そして少しだけ買い増す。
この地道な行動が、数年後に大きな果実となって返ってきます。
長期投資は、感情の戦いであり、信念の継続です。
今日感じた不安や焦りは、決して無駄ではありません。
それを乗り越えるたびに、投資家としての“筋力”がついていく。
そしていつか、穏やかな相場の中でチャートを眺めながら、
「そういえば、あのときの暴落が一番の買い場だったな」と笑える日が来ます。
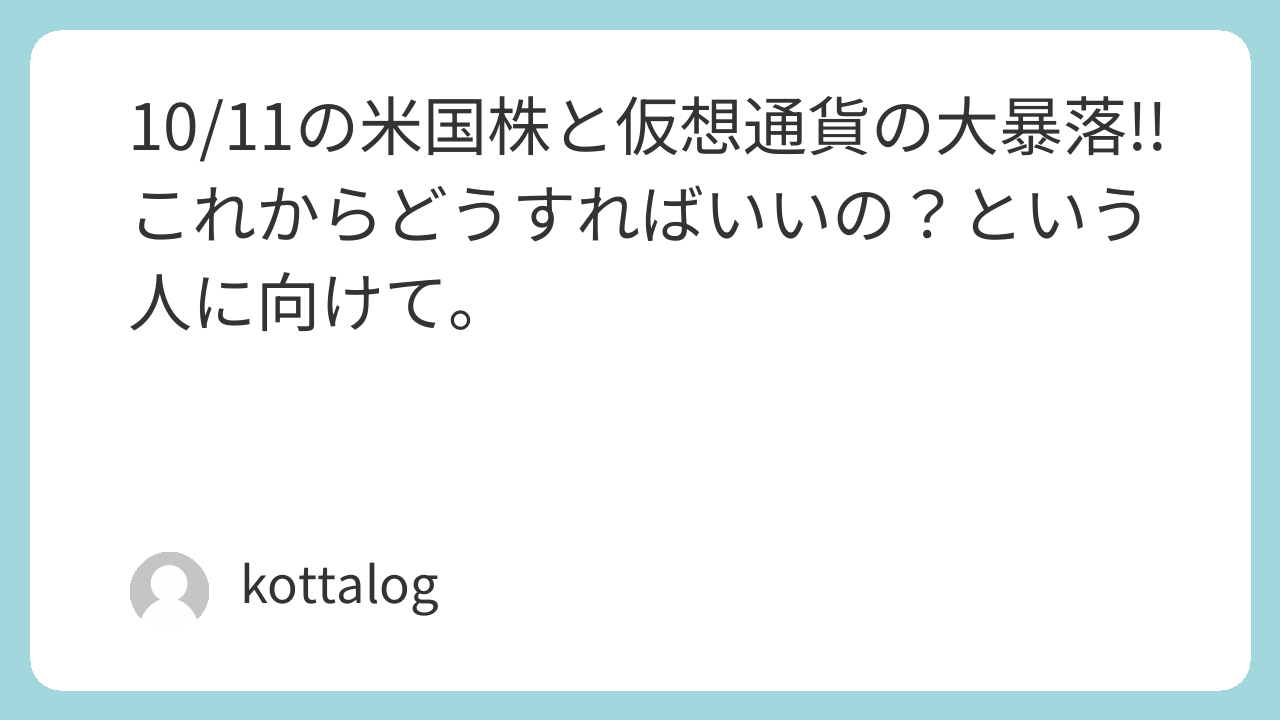
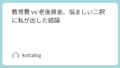
コメント